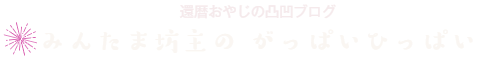ニワトリの思い出
子どもの頃、家でニワトリを飼っていました。私が飼っていたわけではなくて、私が生まれる前からどうやらいたようです。そのほかに、ヤギもいましたし、なんか黒い大きな生き物がいたような記憶もあるので、牛もいたはずです。もちろんペットではなくて家畜ですね。
ニワトリは卵をとるため、ヤギは乳を搾って飲んだ記憶があるのですが、定かではありません。牛については、数年前、父に聞いた話によると、農耕用として飼っていたそうです。実家は農家ではありませんでしたが、昔の田舎の家には必ずニワトリやらヤギやら、家畜がいたものでした。
あの黒い牛はいつの間にかいなくなってしまったのですが、どうしたんだろう。父に聞いてみても、「どこかに売ったかなあ、それとも潰して食べたかなあ」とよく覚えていないようでした。
ニワトリはケージに4~5羽飼われていて、毎朝、卵を取りに行くのが楽しみでした。まだ温かい産みたての卵で、毎朝卵かけご飯を食べたものです。今から考えると贅沢な朝ごはんでした。
卵とニワトリ、最強の食材

それにしても、卵というのはすごい食材です。
生でも食べられるし、茹でてよし、焼いてよし、蒸してよし。卵単体というよりも、他の食材との組み合わせでいろんな料理が作られています。
ためしに「オレンジページ」のウェブサイトで「卵料理」と入れて検索してみたら、462種類もの料理が出てきました。毎日作っても一年ではすべて作りきれないということになります。
料理だけでなく、ケーキ、プリン、クッキーなどのお菓子、パスタやラーメンなどの麺、パンなど、食材としての卵の応用範囲は最も広いのでないかと思います。
栄養の面でも、卵にはビタミンCと食物繊維以外の全ての栄養素が含まれているそうです。
一頃、卵はコレステロールが多く含まれているので、食べるのは1日に1個までにしましょうと言われていました。卵1個に含まれるコレステロール値は約210mgですが、卵を2個食べると400mg以上になり、1日あたりの目標量の約3分の2の量を卵だけで摂取してしまうことになって、多すぎだと考えられていたためです。
ところが、近年の研究の結果、コレステロールは体内で合成されていて、しかも、食べ物から吸収される量よりも3~7倍も多いということが分かり、現在利用されている「日本人の食事摂取基準2015年版」から、コレステロールの摂取基準値がなくなっているのです。
まあ、1日に1~2個くらいなら、毎日食べても大丈夫なのではないでしょうか。
一方の鶏肉です。世界で最も多く食べられている肉は豚肉で世界の肉摂取量の36%。2位が鶏肉で35%ですから、わずかな差。これに卵を合わせればダントツの1位になりますね。
親子が協力して私達に食べられていると考えると、何も文句は言えません。そこまでして、人間に尽くしてくれていたのか。
特に親子丼は涙なくして食べられません。親子で命を捧げてくれているのですよ。こんな料理ありますか?
「全国やきとり連絡協議会」のウェブサイトをみると、焼き鳥メニューとして「ねぎま」「つくね」「ささみ」「手羽」「もも」「皮」「小肉」「はつ」「きも」「砂ぎも」「ムネ軟骨」「ヒザ軟骨」「ぼんじり」「玉ひも」「とさか」の15種類が挙げられていました。
竹串に挿して焼くだけの料理で15種類ですよ。豚や牛にこんなことできますか?
ニワトリと卵の食材としての素晴らしさを改めて認識しながら、ニワトリ・ウインナーを作りました。
ニワトリウインナーを作ってみた
材料
- 胴体・頭 → ウインナー
- 羽・足・トサカ・嘴 → ニンジン
- 目 → スライスチーズ
- 瞳 → 海苔
作り方
ポイントは、ウインナーを真ん中よりややずらして斜め45度に切り、180度回転させてパスタ麺でつなぐと、ニワトリの胴体と頭の形になります。
この時、少し短い方が頭。あとはニンジンやスライスチーズ、海苔で作ったパーツを取り付ければ出来上がり。
クチバシは、四角錐型に切ったニンジンの底面に1cmほどに折ったパスタ麺を5mmほど挿し、出ている部分をウインナーの頭に挿しています。

それにしても、世の中にニワトリがいなかったら、今頃どうなっていたやら。
カーネル・サンダースがフライド・チキンのフランチャイズ・チェーンで成功することもなかったでしょう。
コロンブスが茹で卵を立てることもなかったでしょう。
焼き鳥、ローストチキン、唐揚げ、手羽餃子、出し巻き卵、茶わん蒸し、オムレツ、天津丼、親子丼、かつ丼、ニンジンシリシリー、すべて食べられないんですよ! それでもいいんですかぁ!
いや、それでもよくありません。
ニワトリさん、ありがとう。
道具・パーツの作り方・組み立て方についてはこちら。